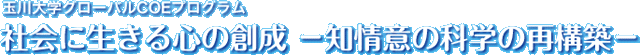【レポート】
玉川大学・カリフォルニア工科大学 ジョイントレクチャーコース2011
玉川大学・カリフォルニア工科大学 ジョイントレクチャーコース2011
「社会行動の科学的理解 ~遺伝子、細胞、認知レベルからのアプローチ~」
日時:2011年6月7日~8日
会場:京都大学百周年時計台記念館


「社会に生きる心の創成」という壮大な目標を掲げた玉川グローバルCOEによるメインイベントの一つとして、毎年開催してきた玉川-Caltech合同レクチャーコース。本学ならびに連携拠点であるカリフォルニア工科大学においてさまざまな側面から脳の機能にアプローチしている大学院生、博士研究員、そして教員が一同に会し、毎年定めるテーマについて世界最先端で研究を牽引している講師をお招きし、みっちりとレクチャーを行って頂き、活発な議論を交わしてきました。
この大変に中身の濃いレクチャーコースも5回目を迎えました。この最先端の脳科学の理解を広く促すため、昨年からは、本学とカリフォルニア工科大学に加えて、他大学(昨年は慶應大学、今年は京都大学霊長類研究所)にも主催に加わって頂き、国内外のより多くの脳科学研究者にご参加頂けるよう規模を拡大させてまいりました。特に今年は、国際意識科学学会という国際学会のサテライトシンポジウムとしても位置づけ、海外からも多くの研究者にご参加頂き、総勢212名(内訳:玉川GCOE関係者56名、国内他研究機関より124名、海外の他研究機関より32名)というこれまでで最大の規模で盛大に開催することができました。もう一方の主催者である京都大学霊長類研究所にご協力頂いたおかげで、会場も、盛大なレクチャーコースに相応しく、京都大学の象徴である時計台の中の大ホール他、いくつかのホールを利用させて頂きました。
しかし、今回の特色は何よりテーマです。いよいよ「社会に生きる心」という本丸にアプローチすべく、「社会行動の科学的理解」にターゲットを設定しました。しかも、遺伝子レベルから、細胞レベル、認知レベルまで含み、種間比較による進化的アプローチまでを盛り込むという非常に欲張ったメニューを用意しました。
初日、朝9時の受付開始と共に、国内外の参加者が続々と集まり始めました。メイン会場の大ホールには、優雅なBGMが流れる中、これから始まるレクチャーコースに対する期待感が満ち溢れていました。
脳科学研究所長の木村先生が紹介によって登壇した最初の講師は、カリフォルニア工科大学のRalph Adolphs教授。感情と社会性の脳内中枢である扁桃体のはたらきについて、緻密な論理構成で壮大な枠組みを提供して頂きました。
ランチタイム後に登壇したのは、京都大学霊長類研究所の中村克樹教授。社会性と遺伝子とをリンクしていくための画期的なモデル動物としてコモンマーモセットの一連の研究をご紹介頂きました。3番目は、カリフォルニア工科大学の出馬圭世博士。人に特有の、「よい評判」を得ることを目的とした意思決定の脳内機構、そしてそれが高機能自閉症者では特異的に傷害されているという最新の画期的な所見を報告して頂きました。初日のトリは、京都大学霊長類研究所所長の松沢哲郎教授。客観性を保ちつつも、研究を始めたばかりの大学院生も世界の第一線の研究者も分け隔てなく、チンパンジーの行動の凄さとその心の世界に引き込む話術はもはや芸術と表現した方がよいように思われました。しかもチンパンジーの世界から逆に人の心の特性を浮き彫りにする研究は科学としても画期的な成果でした。
レクチャーの後は、ポスターセッション。コーヒーブレイクと併せて、コーヒーを飲みながら、それぞれのポスターの前では所狭しとばかりに活発なディスカッションが展開され、ポスター会場全体が熱気に包まれていました。こんなことならコーヒーやスナックの設置場所を狭めて、ポスターの設置場所にもっと余裕を作っておくべきだったと後悔させられたほどです。ポスターは全部で44演題。うち、約半分が玉川GCOE関係者の演題で、残りの半分は国内外の他大学からの演題でした。
その後は、これまた時計台の中にあるフレンチレストラン「ラ・トゥール」を借り切っての懇親会。世界中から集まった第一線の研究者に大学院生も混じって、あちこちでディスカッションが盛り上がっていました。飛び交う言葉も、半分は英語、半分は日本語くらいの割合だったように思われました。
日付は変わって2日目。最初の講師は、乳幼児の模倣研究で世界的に著名な、京都大学教育学研究科の明和政子准教授。乳幼児ばかりか、胎児の知覚、学習にまで研究対象を拡げ、生得的なものと獲得的なものとの境界を鋭く問い直す成果を紹介して頂きました。次は、東京大学医学研究科の山末英典准教授に、社会性の性差やそれに関連する脳部位の灰白質の大きさが、Autismの脳の形状と密接な関係があること、さらに神経伝達物質オキシトシン受容体の遺伝子型との関連について、非常にクリアーに紹介して頂きました。続いて、カリフォルニア工科大学のColin Camerer教授。神経経済学の世界的リーダーである彼は、心の理論を取り込んだ、これからの神経経済学研究について、新たなデータも加えて講義されました。
ランチタイム後の最初の講師、ニューヨーク州立大学のTurhan Canli准教授は、最近注目を集めている、社会行動へ影響を及ぼす遺伝子の発現に対する環境要因の影響、いわゆる"epigenetic"な効果について、包括的なレクチャーをして下さいました。最後の講演者として登壇されたのは、理化学研究所の藤井直敬チームリーダー。日本人離れした巧妙な語り口で、社会神経科学は神経科学の一分野なのではなく、神経科学が社会神経科学の一分野であると喝破し、複数個体の全脳記録を目指して独自開発したECoGシステムを紹介されました。
社会性をキーワードに非常に広範なテーマを扱ったレクチャーコースでしたがどのレクチャーに対しても、会場からは活発な質疑応答が交わされ、講師の先生方も参加者の方々も皆、口々に「多様なトピックスをまとめた非常にいいシンポジウムだ」と絶賛して下さいました。
終わってみれば、このように大成功を収めることができた今回のレクチャーコースですが、開催までには、実に多くの苦難を乗り越えて初めて実現できた会であったことを最後に付け加えさせて頂きたいと思います。とりわけ、開催準備をしている真最中の3月11日に東日本大震災が起き、海外からの参加者の大量のキャンセルが心配されました、実際、同時期の他の多くの学会、シンポジウムが次々と中止に追い込まれていきました。そんな中で、今回のレクチャーコースは、国際意識科学学会とも足並みを揃えて、敢えて実施するという選択をしました。オーガナイザー挨拶の中でも触れさせて頂いた通り、「日本の科学研究を絶え間なく推進するのだ」という強いメッセージを国内外に発信したいと考えて、そうさせて頂きました。このような大胆な選択をし、レクチャーコースを成功に導くことが出来ましたのは、坂上拠点リーダーをはじめ、玉川GCOE関係の研究者・学生を含む全ての参加者の科学に対する真摯さと決意、そして、労を惜しむことなくこれを支持し、多大なご苦労を積極的にかってくださった研究促進室の方々のおかげです。担当者として心よりの感謝を、ここに表させて頂きたいと思います。ありがとうございました。
| 文責 | 松元健二 (玉川大学脳科学研究所 教授/玉川大学グローバルCOEプログラム研究協力者) |
|---|
2011年6月7日(火)〜8日(水)にかけて、「国際意識学会(ASSC)」のサテライトシンポジウムとして「玉川大学−カリフォルニア工科大学 ジョイントレクチャーコース」が、京都大学百周年時計台記念館にて開催された。テーマは「社会行動の科学的理解へ~遺伝子、細胞、認知レベルからのアプローチ~」であり、社会性についての研究に従事し、第一線でご活躍されている様々な分野の先生方にご講演いただいた。本活動報告では、2日間の講演を通して私自身の印象に残った2人の先生のご演説を以下にまとめ、最後に全体を通しての感想をまとめる。
Ralph Adolph (Caltech, USA)「The amygdala, autism, and social cognition」
相手の表情を見つめ、そこから感情を読み取ることは、他人とコミュニケーションをとる際の重要な要素の1つである。従来、自閉症 autism の患者はこのような能力に障害が起きることが知られており、この障害を引き起こす神経学的な仮説としては扁桃体amygdalaの機能異常が関係していると言われている。古くは死後実験において自閉症患者の脳は形態学的・立体解析学的に異常を示しているという報告があり、近年ではfMRI実験において自閉症患者の扁桃体は社会的な行動を要求されると異常な活動を示すということが報告されている。このような報告に基づき、扁桃体が社会的行動に関わっているのかという仮説をより詳細にかつ直接的に調べるための研究を行われたのが、カリフォルニア工科大学のRalph 先生である。 Ralph 先生の本レクチャーコースでのご講演は、ウルバッハ・ビーデ病により両側の扁桃体が障害された患者、自閉症患者、健常人に様々なテストを行わせた結果、扁桃体が社会行動の形成にどのように関わっているのかを調べた研究内容についてであった。まず、扁桃体損傷患者、自閉症患者、健常人の、相手の表情から感情を読み取る際の視線計測をしたところ、健常人は主に相手の目を見るが、扁桃体損傷患者と自閉症患者は違っていることがわかった。扁桃体損傷患者は主に鼻を、自閉症患者は口を中心に見つめていた。さらに、自閉症患者が表情から感情を読み取る際の単一神経細胞記録Single Unit Recording を行ったところ、目や鼻を見ている際は活動を示さない扁桃体の細胞が、口を見つめた時のみ顕著な活動を示していた。また、自閉症を診断するために用いるテスト(Autism Diagnosis Observation Schedule (ADOS), Social Responsiveness Scale(SRS)など)を扁桃体損傷患者に行わせたところ、自閉症の兆候が見られないことがわかった。このような実験結果からRalph 先生は、扁桃体は表情から感情を読み取ることに関わってはいるけれども、なぜ目や鼻ではなく口からから感情の情報を読み取る行動を起こしているのか、強いては社会的行動を引き起こしているのは、扁桃体以外の脳部位が関わっている可能性が強く、扁桃体を含めた機能的な結合ネットワークによって社会的行動は形成されるのではないかと主張されていた。
Keise Izuma (Caltech, USA)「Social Reward Based Decision-Making in Humans」
近年、ヒトを対象にした意思決定Decision-Making の研究は数多くあるが、中でも、意思決定を社会行動として捉え、その神経メカニズム解明を目標としている研究は少ない。その数少ない研究者の一人であるカリフォルニア工科大学のIzuma先生は、ヒトを用いたfMRIの実験により、他人に評価されることがエージェントの行動にどのように影響を与え、またその評価が脳のどの部位でどう表現されているのかについてのご研究をされている。本レクチャーコースでは主にその一連の研究内容についてご演説された。従来、線条体Striatumは報酬rewardに基づく意思決定に関わる部位として有名であるが、報酬と一言でいっても様々な報酬がある。食べ物や飲み物だけではなく、性的刺激や、お金などの二次的な報酬もある。Izuma先生は、報酬がお金 Monetary rewardの場合と、社会的な報酬=他人からの評価 Social rewardの場合で、これら報酬の情報が線条体内のオーバラップした領域に表現されていること、さらに、報酬が他人からの評価Social rewardであるときに限って内側前頭前野mPFCにもその情報が表現されていることを明らかにした。このような一連の実験結果からIzuma先生は、利他的行動をとる人の社会行動において線条体と内側前頭前野が重要な役割を果たしている可能性を説き、複雑なヒトの社会の中で社会的な報酬に基づいて意思決定とる行動を神経学的にアプローチする醍醐味をご教授くださった。
全体を通して
私は、社会性についての研究は、社会行動をうまく引き出すような実験設計をしないといけないことから、従来の研究方法では限界があるように思っていた。しかし、その問題を打破するような様々なアプローチ方法を用いご研究されている先生方の本レクチャーコースでのご講演は、大変刺激的で勉強になった。また、社会性の研究に限ったことではないが、脳機能解明のために神経学的なアプローチをする上で,局在的な脳機能だけでなく全体としての脳機能がどのように成されているのかと考えることは非常に重要であることを改めて認識することができた。
| 報告者 | 野々村聡(玉川大学大学院 脳情報研究科 博士課程後期) |
|---|
2011年6月7日と8日の二日間、玉川大学・カリフォルニア工科大学ジョイントレクチャーコースが、「国際意識学会(ASSC)」のサテライトシンポジウムとして、京都大学で開催された。今回のレクチャーコースでは、「社会行動の科学的理解」をメイントピックに据え、脳科学、分子生物学、経済学、霊長類学、心理学分野といった、様々な研究分野の先生方によるレクチャーが行われた。
初日はYale UniversityのKevin Pelphrey先生のレクチャーがキャンセルとなったため、4人の先生方によるレクチャーが行われた。カリフォルニア工科大学(Caltech)のRalph Adolphs先生は表情認知における扁桃体の重要性について、扁桃体損傷患者の例やfMRIを用いた研究をもとに紹介され、さらに自閉症との関連を示された。京都大学霊長類研究所の中村克樹先生は社会行動を研究するためのモデル生物として、マーモセットの有用性について紹介された。カリフォルニア工科大学(Caltech)の出馬圭世先生は社会的な報酬である「評判」を用いた意思決定における、前頭前皮質内側部(MPFC)や線条体の重要性を示された。そして、京都大学霊長類研究所の松沢哲郎先生は、これまでに行われてきた、チンパンジーを対象とした一連の研究についてのレクチャーをされた。
初日のレクチャーの中で、特に興味深かったのは松沢先生によるレクチャーであった。松沢先生はヒトをヒトたらしめている特徴はなんなのか、という疑問に答えるため、ヒトに最も近い種であるチンパンジーを研究対象とされており、生息地での観察や研究所での行動実験を行われている。今回のレクチャーでは、ヒトの社会行動を特徴付ける点として、互恵関係(reciprocity)、新生児の仰向けの姿勢(supine posture)、心的表象(representation)を挙げられた。互恵関係の例として、ヒトの幼児が食べ物をも母親に与える行動や、ヒトは子育てが終了した後も、祖母として孫の世話を行うといった点をあげられ、ヒト独自の行動であることを示された。次に、ヒトの進化に関する仰向けの姿勢の重要性を提案された。他の霊長類では、新生児の時期に仰向けの姿勢を取ることができず、なにかを掴むような反射行動を行う。これは、ヒト以外の霊長類は新生児期には母親にしがみついて過ごすためであるが、ヒト場合は生まれてすぐ母親とは距離を取り、仰向けの姿勢で寝るようになる。この結果、顔を向かい合わせたコミュニケーション、母親を呼ぶための発声、自由になった両手による道具利用の学習といった社会的な行動が促進されると考えられます。これまでは、ヒトは直立二足歩行によって、脳の発達や、手指の発達が促されてきたという考え方が主たるものであったが、松沢先生は仰向けの姿勢がむしろ重要ではないかと提案された。そして最後に、心的表象がヒトに特徴的なものであるということを、行動実験から示された。ヒトは、赤色を示す文字や記号があった場合、それらをひとまとめにして「赤」という言語で表象することができる。一方、チンパンジーにはこのような能力はなく、色と形の関係などをそのまま記憶することしかできない。ただ、その記憶能力は人と比べて遥かに優れていることから、チンパンジーは、現在・この場所を理解する能力に長けている。一方で、ヒトに特徴的な能力とは未来を想像する能力である、ということを論じられた。
二日目はEmory UniversityのLisa Parr先生によるレクチャーがキャンセルとなったため、5人の先生によるレクチャーが行われた。京都大学の明和政子先生は、社会認知能力がどのようにして獲得されるのかという点について、ヒト・ヒトの新生児・チンパンジーの行動を比較し、ヒトにおける社会的要素の重要性を示されました。東京大学の山末英典先生は、自閉症患者に見られる社会的行動の欠落の性差に対する弁蓋部の重要性や、その遺伝的原因及び治療対象の候補としてオキシトシンの重要性を示された。カリフォルニア工科大学(Caltech)のColin Camerer先生はゲーム理論を利用し、経済活動における他者との相互作用について話をされた。Stony Brook UniversityのTurhan Canli先生は社会的行動とそれに関連する遺伝子の発現及び発現調節について紹介された。理化学研究所の藤井直敬先生はEcoG電極を用いた霊長類の皮質脳波計測について紹介された。
自身が霊長類を利用した電気生理学実験を行っていることもあり、藤井先生のレクチャーは非常に興味深いものであった。藤井先生はEcoG電極を用いた、皮質脳波の記録を行われている。特に現在は効率的な全脳からの記録に挑戦されており、今回のレクチャーではそのデータの一部を見せていただくことができた。これまでの霊長類を用いた電気生理学研究では、限定的なタスクを行っている動物の、ある脳領域のみから電気活動を記録するという手法がほとんどであった。しかしながら、社会的な行動は局所的な神経活動から生じるのではなく、様々な脳部位での活動が相互に作用する必要がると考えられる。そのため、動物の運動や、姿勢、視線の方向、そして、脳全体の活動を同時に記録することが、社会的行動の神経基盤を調べるためには必須となる。藤井先生はこのようなシステムを開発・使用し、複数の動物が相互作用しながら行動を行っている際の、神経活動を記録されている。そのデータを元に、社会的な環境における、行動の抑制と相関する前頭葉の活動の抑制などを示されたが、このように記録されたデータの量は非常に膨大なものとなり、その解析は非常に困難となる。先生は、その解析に世界中の研究者の協力を得ようと、データを公開するwebサイトを立ち上げられている(http://neurotycho.org)。このようにデータを公開することは、自らの研究の独自性を失わせかねないが、一方で様々なフィールドの研究者による解析が期待できるため、その研究の大きな発展を促し得るものである。現在の高度に情報化が進んだ環境を鑑みるに、今後のデータの巨大化・共有化の可能性を予感させるレクチャーであった。
一日目の夕方からは、ポスターセッションが行われ、私の研究に関しても様々な意見をいただくことができた。特に、哲学の研究者と議論を行うことができたのは、今回のレクチャーコースがASSCのサテライトとして開催されたことが大きな理由であったと思う。その夜には懇親会も開催され、他大学・研究所のポスドクや大学院生らと様々な意見を交換でき、非常に有意義な時間を過ごすことができた。
我々の日常生活の大部分は、他者との相互作用を含む社会的なものである。これまでは、その複雑さもあり、社会行動の神経基盤にまで踏み込んだ研究を目にすることは少なかった。今回のレクチャーコースでは、ヒトや動物の行動実験のみならず、電気生理学的手法やfMRIを利用した研究、臨床現場での患者を通した研究や、その遺伝的バックグラウンドを探索する研究など、様々なアプローチで研究が進められていることがわかった。これらの研究手法・研究結果が組み合わさることで、これからの社会行動の科学的理解が大きく進むであろうことを、予感させるようなレクチャーコースであった。
最後になりましたが、このようなレクチャーコースに参加する機会を与えてくださったGCOEプログラム、その開催に尽力された関係者の方々に深く感謝いたします。
| 報告者 | 田中慎吾(脳科学研究所・博士研究員) |
|---|