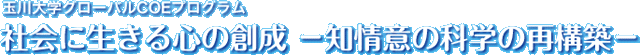【レポート】
脳科学リテラシー部門第8回研究会
「意識の脳科学と哲学」
<10月16日>
○第一部 意識の基礎科学研究
講演1 「『盲視(ブラインドサイト)』の示唆するもの:モデル動物からの知見」
高浦加奈(玉川大学)
○第二部 意識の臨床研究
講演2 「意識障害の評価と治療:特にNeuromodulation療法について」
深谷 親 氏(日本大学)
講演3 「意識障害の臨床倫理:診断基準、リハビリテーション、そして終末期決定」
戸田聡一郎 氏(東京大学)
<10月17日>
○第三部 意識の哲学研究
講演4 「意識の神経基盤と形而上学」
太田紘史 氏(京都大学)
講演5 「意識の高階説と一階説」
佐藤亮司 氏(東京大学)
玉川大学脳科学研究所脳科学リテラシー部門第8回研究会は、2010年10月17日(土)と18日(日)の2日間にわたり開催された。今回は「意識の脳科学と哲学」をテーマとし、全体を「意識の基礎科学研究」、「意識の臨床研究」、「意識の哲学研究」の3つの部に分け、計5名の講演者に登壇をお願いした。
第1部「意識の基礎科学研究」では、本大学グローバルCOE研究員の高浦加奈が講演を行った。講演タイトルは「『盲視(ブラインドサイト)』の示唆するもの:モデル動物からの知見」で、大脳皮質一次視覚野(V1)の損傷患者に見られる「盲視」と呼ばれる現象に関する先行研究の紹介と、高浦が以前所属していた生理学研究所の伊佐正教授・吉田正俊助教のグループにおいて行った実験についての報告がなされた。V1は視覚的情報処理に関わる視覚皮質の入り口として知られているが、この部位が損傷を被ると対応する視野において何も見えなくなってしまう。だが、この盲領域に視覚刺激を呈示し、患者にその定位を求めると、主観的には見えていないにもかかわらず偶然以上の高い確率で正答が得られる。この盲視現象は視覚的気づきと視覚的情報処理機能とが乖離しうることを示していると考えられている。盲視に関するこれまでの代表的な知見を紹介したあと、高浦は自らが関わった生理学研究所での実験を報告した。左側V1を切除したサルでは、人間の盲視患者と同様に、右側の半視野において気づきと情報処理機能との乖離が生じていると推測される。だが、サルからは視覚的気づきに関する直接的な言語報告を得ることができない。そこで、高浦のグループでは、視覚的気づきの有無を反映しうるような選択条件を組み込んだ実験デザインを工夫し、強制選択課題におけるパフォーマンスと比較することで、サルにおいてもこうした乖離が実際に生じていることを示した。また、記憶誘導サッケード課題を用いた別の実験では、通常の想定に反して、盲領域に呈示された刺激情報においても作業記憶との結びつきが見られるということが明らかにされた。高浦は、こうした記憶保持に関わる視覚的情報処理機能を担うために、損傷側半球においてV1を経由しない上丘経路が動員され、損傷された機能を補償している可能性があるという見解を述べた。
続く第2部「意識の臨床研究」では、深谷親氏(日本大学医学部)と戸田聡一郎氏(東京大学大学院医学系研究科)にご講演いただいた。
深谷氏は「意識障害の評価と治療:特にNeuromodulation療法について」という講演タイトルでお話をされた。深谷氏は現役の神経科医であり、脳深部刺激法(DBS)を用いたニューロモジュレーション療法の専門家である。講演では、最初に意識の医学的な定義や分類と、視床下部調整系を中心としたその解剖学・生理学について説明がなされた。意識障害に関する病変の在り方は大きく広範性病変と限局性病変に分類されるが、前者は主に特定の意識内容に関わる障害に関連し、後者は主に遷延性意識障害(いわゆる植物状態)などの覚醒障害に関連する。後者の覚醒障害の評価や治療に関して、続いて、深谷氏が専門とするDBSを用いた治療の事例を中心に紹介がなされた。DBSはパーキンソン病などによって引き起こされる不随意運動に対して有効な治療法として認められており、その他にもうつ病や強迫性障害など広範な疾患に対して効果が期待されている。DBSの遷延性意識障害に対する過去の適用事例からは、自然経過による改善に比べると高い確率で意識レベルが改善することが示唆されている。だが、その際にも、必ずしも劇的な効果が見られるわけではなく、より簡便な脊髄刺激療法という別の療法が存在することなどから、その適用事例はパーキンソン病に対するものと比較すると少数に留まっている。講演の最後には、遷延性意識障害では他の脳部位も障害を被っていることが多く、意識障害から脱却したとしても必ずしも生活の質が向上するとは限らない、という難しいジレンマも提起された。
続いて、戸田氏は「意識障害の臨床倫理:診断基準、リハビリテーション、 そして終末期決定」という講演タイトルでお話をされた。戸田氏は意識障害の診断や治療に関わる倫理的問題に関して考察を展開されている生命倫理学者である。最初に、行動上の証拠によって遷延性意識障害と区別される「最小意識状態」に関する説明がなされ、両者の区別が医療資源の配分などの社会的問題や治療停止の判断などの倫理的な問題と関連していることが述べられた。これらの意識障害の患者に対しては脳画像法を用いて脳活動を調べる研究も行われている。その研究によれば、遷延性意識障害や最小意識状態の患者に対してテニスをしている場面と家の中を歩く場面とをそれぞれ想像するよう求めたとき、健常者と同様にそれぞれ異なる脳活動を示すことが確認された。こうした実験結果は意識状態の診断に関する新たな手法を示唆するものであるが、行動学的指標と神経学的指標のどちらを優先すべきかという問題を孕んでいる。続いて戸田氏は、遷延性意識障害に関して高い誤診率が存在することを示した研究に触れた。もし最小意識状態と遷延性意識状態が異なる治療上の判断を要求するものであるならば、このような高い誤診率が存在することはゆゆしき問題である。しかし、戸田氏によれば、最小意識状態に関する疫学的データはいまだ不足しており、こうした両者の異同に関わる問題に答えを与えられる状態にはない。そこで戸田氏は、遷延性意識状態と最小意識状態を積極的に区別していない日本の診断基準に触れ、それが双方の患者に対する均一なケアの提供につながることで、上述の疫学的データの不足を補うという貢献をなす可能性があることを指摘された。
第3部「意識の哲学研究」では、太田紘史氏(京都大学大学院文学研究科)と佐藤亮司氏(東京大学大学院総合文化研究科)にご講演いただいた。お二人とも分析哲学的な手法を用いて意識の研究をされている若手の哲学者である。
太田氏は「意識の神経基盤と形而上学」という講演タイトルのもと、物理主義の特定のタイプを擁護する議論を提示したうえで、機能主義的な観点から意識の神経基盤に関するメタ的な分析を展開された。意識には機能的な側面と現象的な側面が区別できるが、後者の現象的意識(いわゆるクオリア)の存在は、「世界は物理的なものだけから成り立っている」という物理主義的な立場にとって問題であると考えられている。このことを示すのがいわゆる「ゾンビ論法」と呼ばれる思考実験である。ここで言う「ゾンビ」とは、物理的な特徴に関して得られるいかなる証拠によっても普通の人間とは区別できないが、現象的意識だけを欠いているとされる存在である。もしこうした存在が可能であるとすれば、現象的意識の存在は物理主義に反することになる。このゾンビ論法に対する物理主義者からの反論としては、「そもそもゾンビは思考不可能である」というものと、「ゾンビは思考可能だが不可能である」というものと、2つのタイプが考えられる。前者が「タイプA物理主義」であり、後者が「タイプB物理主義」である。タイプB物理主義は「アポステリオリな必然性」という概念に訴え、意識と脳状態の関係は水とH2Oの関係のようなものにすぎず、両者のあいだには経験的な探究によって判明する必然的な同一性関係が成り立つと考えることができると主張する。太田氏はこれに対し、2つのペアにおける関係の在り方を比較分析することで、意識と水のあいだには実際のところアナロジーは成立していないと論じ、タイプA物理主義を擁護する。続いて、いかにして現象的意識とその神経基盤との説明ギャップを解消するかという問題を論ずるために、物理主義的な立場のひとつのオプションである機能主義からの説明戦略について考察が行われた。機能主義においては、説明すべき対象はまず機能のクラスターへと分解され、さらに個々の機能について詳細な機能分析が行われたのちに、しかるべき機能の占有者として物理的基盤が同定される。太田氏によれば、意識の機能を「表象」として捉え、そうした表象機能に関する中間的な機能分析を進め、最後にその占有者を同定するという戦略をとることで、説明ギャップは乗り越えられると考えられる。この点で、機能主義や表象主義と組み合わされた物理主義は意識の問題を解決するうえで有望な立場であると言える。
最後の発表者としてご登壇くださった佐藤氏は、「意識の高階説と一階説」という講演タイトルのもと、二つの問題を中心に議論を展開された。それは、第一に、現象的意識は何らかの認知的アクセスを必要とするかという問題であり、第二に、そうした認知的アクセスはどのようなものでなければならないかという問題である。哲学者のネッド・ブロックは「現象的意識」と「アクセス意識」を区別し、現象的意識は認知的アクセスなしに成立しうるという主張を展開している。ブロックは近年、変化盲パラダイムに基づくランドマンらの認知心理学的な実験を利用して、現象的意識の容量はアクセス意識の容量を超過しており、したがって現象的意識の内容はアクセス意識の内容になりうる以上のものを含んでいるという議論を行っている。佐藤氏によれば、このランドマンらの実験結果はアクセス意識に段階性を設けることで整合的に再解釈できるのであり、それゆえブロックの議論は必ずしも決定的なものではない。また、両義図形の知覚やカクテルパーティー効果といった諸事例を踏まえるならば、経験はつねにある種の解釈を含んでおり、概念習得によって現象的経験は変化しうると考えられる。だとすれば、第一の問題に対しては、現象的意識は何らかの認知的アクセスを必要とすると答えられる。では、どのような認知的アクセスが必要なのだろうか。佐藤氏は、グローバルワークスペース(GW)理論と高階思考説の対立を通して、この問題に対する考察を行った。GW理論によれば、ある心的表象が意識的なものとなるためには、その表象がGWにアクセスしていなければならない。これに対して、高階思考説によれば、ある心的表象が意識的なものとなるためには、単にGWにアクセスを有するだけではなく、その心的状態を対象とする高階の思考が伴っていることが必要である。佐藤氏は、認知神経科学者のラウらによる実験を取りあげ、その実験結果は高階思考説を支持する証拠を与えており、そうした高階思考を担う神経基盤としては中背側前頭前野が候補として挙げられると論じた。それゆえ、第二の問題に対しては、現象的意識に必要な認知的アクセスは高階思考であると答えられる。
以上、いずれの講演も大変興味深いものであり、各講演後にはそれぞれ会場を巻き込んで熱心な質疑応答が行われた。本研究会を通じて、意識の問題が各分野の協働を必要とする奥行きと広がりをもつものであることが再確認できたように思う。この点で、本研究会はいずれの参加者にとっても大きな意義をもつものであったと言えよう。
| 日時 | 平成22年10月16日(土)13:30~18:00/10月17日(日)10:00~13:10 |
|---|---|
| 場所 | 玉川大学 研究・管理棟 5階507室 |
| 報告者 | 小口 峰樹(玉川大学GCOE研究員) |