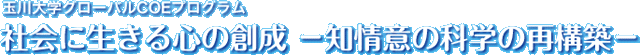【レポート】
グローバルCOE キックオフシンポジウム
『今求められている脳科学研究』
■ プログラム ■
13:00 開催挨拶 小原芳明(玉川大学学長)
13:10 『玉川大学の脳研究のこれまでとこれから』
塚田 稔(玉川大学脳科学研究所副所長・玉川大学21世紀COEプログラム
「全人的人間科学プログラム」拠点リーダー)
13:40 『玉川大学グローバルCOEプログラム「社会に生きる心の創成」』
坂上雅道(玉川大学脳科学研究所教授・玉川大学グローバルCOEプログラム
「社会に生きる心の創成」拠点リーダー)
14:10 『玉川大学脳科学研究所の研究紹介』
丹治 順(玉川大学脳科学研究所所長)
14:40 『言語発達と脳科学』
佐藤久美子(玉川大学脳科学研究所/玉川大学リベラルアーツ学部長)
15:00 特別講演『脳科学が教育に示唆するもの』
津本忠治氏(理化学研究所脳科学総合研究センターグループディレクター)
15:50 閉会の挨拶
現代という複雑な時代に生きる人間についての総合理解を目指して玉川大学脳科学研究所が提出したプロポーザル、「社会に生きる心の創成プログラム」は平成20年度文部科学省グローバルCOE研究拠点が推進する学術研究事業として採択された。これを記念して玉川GCOEキックオフシンポジウム「今求められている脳科学研究」が2008年10月25日に開催された。本シンポジウムでは、本研究所のこれまでの歩みとその研究戦略についての俯瞰的説明、および時代の求める脳科学研究についての総説講演と事例報告が行われた。
小原学長の開会挨拶に続いて行われた、塚田稔教授による講演「玉川大学の脳研究のこれまでとこれから」では、本学の脳研究は当初ただひとつの研究室からスタートしたこと、そして選任研究員も最初唯一人のみであったが現在では100人を数えるまでに成長を遂げたこと等が紹介された他、大学全体の教育理念である"聖・健・富・真・善・美"に合致した教育の科学的根拠を解明する研究テーマとして、人間の脳についての研究はいわば必然であると言っても過言ではないほどに多面的で深淵な魅力に満ちていたこと、等の説明があった。
そして、脳の機能に関する様々な側面からの研究を通じて玉川大学脳科学研究所が最終的に目指すものは、脳の情報創成メカニズムの解明であり、K-16から大学院へと続く、玉川が誇る全人的な教育プログラムの中にそのメカニズムを実装し、そこでの学習体験を豊かな情報の創成としてアウトプットできる科学的に整備された教育環境の実現であることが強調された。更にこれらを遂行することにより期待される具体的な成果の応用例として、脳科学リテラシーのための学校教育レベル別に編集されたテキストの編集、大学院脳情報専攻課程教育の個性別にチューニング可能なカリキュラムデザイン等、ユニークな視野と基礎知識を持った研究者・大学院生養成のための展望が紹介された。
次に行われた坂上教授による講演では、今回採択されたGCOEプログラムについて、塚田講演で解説された運営理念を着実に実現する為に必要な具体的推進施策と期待される学術的研究成果についての説明が、示唆に富む予備的事例報告とともに行われた。まず、本GCOEが標榜する学際的脳科学研究というアプローチが、玉川学園の標榜する全人教育という伝統的教育理念の推進にとってどのような意義を持ち得るかについての説明では「新しい形式による人の心と社会の科学的理解」という統一研究目標が示され、本GCOEで実施される脳科学研究では「倫理観」、「友愛観」、「経済観」という、人間において社会活動の基盤をなすこれらの規範的価値観を抽出し、それぞれの領域に適用すべき種々の理論的思索および実験的介入の集中的な展開をもってその活動の中心に据えるという、研究の実質的なアウトラインが示された。そこで強調されたことは、これからの脳科学は「個」としての脳単体のみを研究対象とするのではなく、社会や文化を構成する個々人の精神が集団という環境内で相互影響のもと発揮する、その集合的な働きに注目した「社会脳」についての研究こそが重要であるということ。言い換えれば、これからの脳科学は我々の脳が実際のところ日々典型的に遭遇する動作環境を考慮した条件のもとでこそ精力的に研究を推進するべきである、というものであった。
こうして設定された研究ゴールを達成する為に講演の後半ではfMRIを始めとする高度な計測機器および運用設備群、優秀な実績を持つ国内研究スタッフ、カルフォルニア工科大学をはじめとする海外有力研究機関との共同研究ネットワーク等が紹介され、併せて我が国を代表する学際的脳科学トレーニングセンターの確立を目指し厳選された指導教授陣、内外高等教育機関からの質の高いポスドク受け入れ状況が紹介された。
坂上講演に続いて行われた脳科学研究所所長丹治順教授の講演「玉川大学脳科学研究所の研究について」では、始めに脳科学研究所の全体概要として、本研究所の三つの研究センターである脳科学研究センター、知能ロボット研究センター、言語情報研究センターが紹介され、その後各研究センターで現在進行中のホットな研究トピックスとしてブレイン・マシン・インターフェイス(BMI)やホームユースを想定したロボットコミュニケーション、さらに幼児の学習パフォーマンスと母子コミュニケーションなどの概要が紹介された。更により基礎的な関心に立脚した研究事例として、記憶と意思決定および行動選択を対象とする研究成果の中から海馬記憶に関する数学的モデルの構築と動物実験から特定に成功した運動-概念系の情報変換に関与する脳内神経細胞についても紹介が行われた。
丹治講演の後は本研究所言語情報研究センター主任の佐藤久美子教授による「言語発達と脳科学」と題した研究事例紹介が行われた。幼児期の言語習得における意味の聞き取りおよび産出における母子相互作用をめぐる発達心理学的アプローチによる行動観察、およびその結果を説明する一時記憶的なメカニズムに対する認知科学的な仮説の適用を中心とした報告には会場からの質問も数多く出され、熱気をおびたディスカッションが交わされた。
そして本キックオフシンポジウム最後の講演は、理化学研究所脳科学総合センター塚本忠治氏による「脳科学が教育に示唆するもの」と題した総説レクチャーが行われた。本レクチャーでは過去から現在に至る認知発達とその応用を対象とした神経科学研究の流れが概観され、特に教育実践に対する示唆的な知見として、神経発達パターンの特徴と脳機能の感受性期に関する話題が取り上げられた。まず既報の事実として異なる脳機能に対応して複数の感受性期が存在することが示され、さらに最近の研究から感受性期終了後の緩慢な回復というヒトと動物双方に発見された事例を通して神経発達の臨界期(感受性期)以降における可塑性神経活動の発現可能性が指摘された。更にヒト行動神経発達学的には帰結的な事象であるとともに、教育論・社会論的には喫緊の課題として昨今認識の度合いがとみに高まりつつある、学童期を通じた社会性の獲得の問題が取り上げられた。このトピックでは情動を認知する能力、中でも顔の表情からの情動認知が非常に重要であることが、サルの親子を用いた比較認知論的実験の研究事例から紹介され、聴衆の反応も非常に大きく強い印象を受けた様子が見られた。






| 日時 | 2008年10月25日(土)13時00分~16時00分 |
|---|---|
| 場所 | 玉川大学視聴覚センター104教室 |
| 報告者 | 勝尾 彰仁(玉川大学リベラルアーツ学部・准教授) |