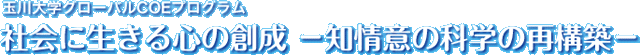【レポート】
脳科学リテラシー部門 第10回研究会
「記憶と証言」
「記憶研究の脳科学リテラシー」
中澤 栄輔(東京大学グローバルCOE「共生のための国際哲学教育研究センター」特任助教)
「記憶と嘘」
藤井 俊勝(東北大学大学院医学系研究科 准教授)
「子どもの証言:出来事の記憶をどう聞くか」
仲 真紀子(北海道大学大学院文学研究科 教授)
脳科学リテラシー部門研究会は、脳科学研究者と哲学をはじめとする人文科学系研究者との間での学術的な交流や意見交換を促進する目的で、毎回特定のテーマを設けて開催されている。第10回目となる今回は「記憶と証言」をテーマとして3名の専門家からご講演を頂いた。
2011年10月8日(土)、玉川大学脳科学研究所脳科学リテラシー部門研究会が開催された。第10回目となる今回のテーマは「記憶と証言」である。記憶には意味記憶や手続き記憶などさまざまな種類が存在するが、今回は特に個人の体験した出来事に関する記憶である「エピソード記憶」に焦点が当てられた。個人が有するエピソード記憶は、時として、司法や福祉などの場における証言を通じて、何らかの出来事に関する「証拠」として重要な社会的機能を担う。だが、ここ数十年の記憶研究は、エピソード記憶がいかに無自覚的な情報の欠損や捏造を被りやすいかを明らかにしてきた。では、こうした記憶の歪みはどのような要因によって引き起こされるのだろうか。そして、記憶が歪みに対する脆弱性を抱えているという事態を前にして、われわれは記憶のもつ社会的機能をどのように評価し、記憶をめぐる社会環境をどのように構築してゆけばよいのだろうか。本研究会では、こうした問題意識に基づいて、3名の専門家の方にご登壇をお願いした。
最初にご登壇された中澤栄輔氏(東京大学グローバルCOE「共生のための国際哲学教育研究センター」)は、「記憶研究の脳科学リテラシー」というタイトルのもとで、ご自身が関わってこられた研究開発プロジェクト「文理横断的教科書を活用した神経科学リテラシーの向上」の内容を中心にお話をされた。当該のプロジェクトは2006年から2009年にかけて行われ、その成果として『脳神経科学リテラシー』という大学講義向けの教科書が出版されている。中澤氏ははじめにプロジェクトの概要を紹介し、氏が行ってきたリテラシー教育に関して、特に教科書のなかでご自身が執筆を担当された記憶の章に対応する授業内容を中心に説明を行った。脳神経科学リテラシーの授業では、脳神経科学に関する知識の涵養だけではなく、脳神経科学の知見が社会や人間観に対してどのような影響を及ぼす(あるいは及ぼしうる)かについての理解を得ることが目指される。氏は、これまでのご自身の教育実践に対してメタ的な考察を加えた上で、そもそも科学リテラシーという概念をどのように理解するべきかという問題を掲げ、二十世紀における科学リテラシーの研究史をたどりながら分析を加えた。中澤氏は、科学リテラシー概念の歴史的変遷を踏まえ、当該概念を捉えるための枠組みとして、「欠如モデル vs. 対話モデル」、「標準化モデル vs. 文脈モデル」、「科学応援型 vs. 科学批判型」という三つの次元を設定できるのではないかという提案を示した。氏は終わりに、この枠組みは現在のところ作業仮説にすぎないが、科学リテラシーに関するさまざまな見方をこの枠組みのなかに位置づけることで、概念的な混乱を避けつつリテラシー教育に関する実践を整理できるかもしれない、という展望を語った。
続いて登壇された藤井俊勝氏(東北大学大学院医学系研究科)は、「記憶と嘘」というタイトルで、ご自身のグループが行ってきた記憶に関する脳画像法を用いた脳機能研究および臨床神経心理学研究に関してお話をされた。氏ははじめに「嘘」と「だまし」に関する概念規定を行い、嘘を「意図の有無にかかわらず誤った内容の発話を行うこと」として、だましを「内容の真偽を問わず相手を欺く意図をもって発話を行うこと」として定義した。具体的な実験結果としては、まず、氏が治療にあたった、前頭基底部に損傷を被った患者の事例が紹介された。この患者は逆行性健忘に加えて前向性健忘も示し、しばらくのあいだ事故後に経験した出来事を想起することができなかった。しかし、脳内の浮腫が回復するにつれ、徐々にそれまで思い出せなかった事故後の出来事を語りだすようになった。事故後の出来事は記憶として保持されていなかったのではなく、保持されていたが想起されえなかったと考えられる。つまり、当該の患者は記銘や保持ではなく想起に関する選択的な障害を負っていたのである。ここから、損傷部位である前頭基底部は記憶のなかでも特に想起に関わっているということが示唆される。これにヒントを得て氏が行った健常者に対するPET実験からは、この仮説に対して支持を与える結果が得られた。氏はさらに、嘘とだましが乖離した実験デザインを工夫することで、嘘とだましがそれぞれ前頭前野の異なる下位領域と関係し、だましには特に扁桃体も関与しているということを示した実験や、パーキンソン病患者が「嘘をつかない」のか「嘘をつけない」のかという問いに対し、嘘反応の成績と前頭前野の活動の相関を見ることで、後者の可能性を支持するデータを示した実験、そして、乖離性の逆行性健忘患者が示す、個人史におけるある時期に限定された記憶喪失に対して、右前頭前野背外側部が関与していることを示した実験などを紹介した。これらの実験結果は記憶やその歪みに関する神経基盤の解明に寄与するものである。
最後に登壇された仲真紀子氏(北海道大学大学院文学研究科)は、「子どもの証言:出来事の記憶をどう聞くか」というタイトルで、証言の問題に対する心理学的なアプローチについてお話をされた。氏は「犯罪から子供を守る司法面接法の開発と訓練」プロジェクトを2008年に立ち上げ、子どもから正確な情報を得るための面接法の開発を進めるとともに、司法や福祉の現場の担当者に対して精力的に面接法の研修を行っている。発表において氏は、まず、子どもにおける記憶の歪みがどのような要因に基づいて生じるのかについて、関連するいくつかの実験に触れながら分析を行った。子どもは概して記憶に関するソースモニタリング能力が未発達であり、目撃証言などにおいてさまざまな暗示作用に影響される傾向がある。実際、聞き手の促しによって、子どもが実際には体験していない出来事に関して生き生きと記憶を語りだすことも少なくない。氏が行った実験では、聴取に先立って視覚的なイメージを形成したり、外部から何らかの情報を与えられたりした場合に、記憶に対する汚染がより強く生じるということが示された。こうした事態を踏まえるならば、より正確な証言を得るためには、被暗示性の影響を可能な限り排除したかたちで聴取が行われなければならないだろう。氏が開発を進めている司法面接法においては、記憶の汚染を防ぐために自由報告が重視され、面接者からの情報提示は極力排除される。また、面接者が子どもの言葉に対する解釈や評価を行うことも避けられる。そうした要素も暗黙のうちに子どもの証言にバイアスをかけてしまう可能性があるからである。氏は最後に、自身が関わり、日本学術会議で議決された提言「科学的根拠にもとづく事情聴取・取調べの高度化」に触れ、日本における司法面接環境の問題点や改善すべき点について指摘を行った。 以上、各講演とも独自のアプローチから記憶と証言をめぐる問題に迫るものであり、発表後には会場を巻き込んで熱心な質疑応答が行われた。記憶はその成り立ちからして本質的に脆弱性を抱えているが、だからといって、それがもつ証言としての社会的な機能を捨て去ることはできない。それゆえ、われわれは記憶やその歪みのメカニズムの解明を今以上に進め、その知見に基づいてより確かな証言を得られるような社会環境を準備してゆく必要がある。そのためには、まさに本研究会が企図したように、脳科学・心理学・哲学など、異なる研究分野が手を携えて問題解決に臨むことが肝要であろう。
| 日時 | 2011年10月8日(土)13時00分~18時30分 |
|---|---|
| 場所 | 玉川大学研究・管理棟 5F 507室 |
| 報告者 | 小口 峰樹(玉川大学GCOE研究員) |